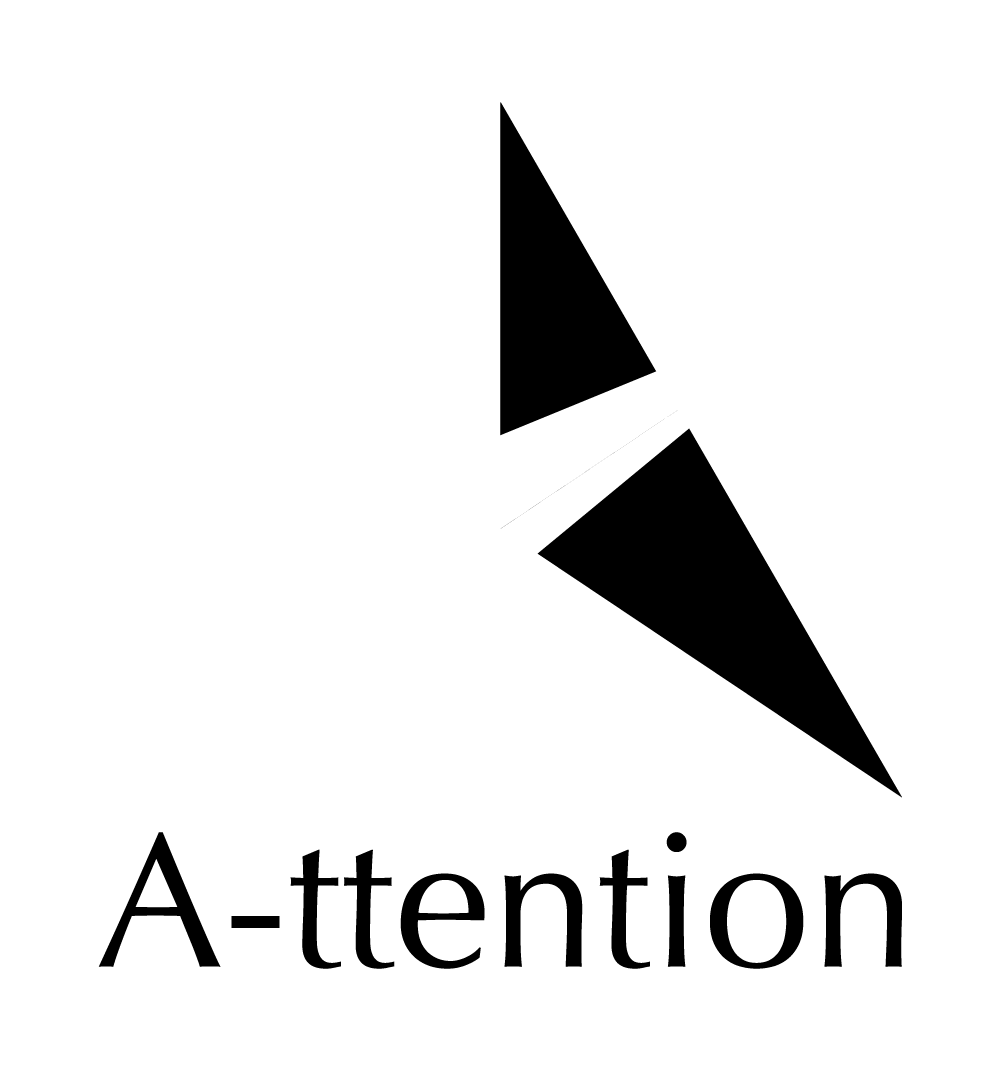ユグノー戦争(ユグノーせんそう、フランス語:Guerres de religion, 1562年 - 1598年)は、フランスのカトリックとプロテスタントが休戦を挟んで8次40年近くにわたり戦った内戦である。. 世界の大多数の人々が信仰するキリスト教には、カトリックとプロテスタントの二つの宗派が存在します。仏教が主な宗教である日本では、あまり馴染みが無く違いがよくわからない人も多いでしょう。今回は、そんなカトリックとプロテスタントの違いについてご紹介します。 宗教改革. 例えば、プロテスタントと比較して、カトリックの学校では毎朝礼拝を行うことが少ない、生活指導が厳格であると言われます。 建学母体がフランスのカトリック系の学校ではフランス語の授業が行われることもあります。 © 2021 Rekisiru All rights reserved. 1941(昭和16)年、真珠湾攻撃からはじまったアメリカとの戦争は、すべての人にとって、大きな悲劇となりました。 被爆の聖母(長崎・浦上教会) カトリック教会も大きな苦しみと損害を受けました。信徒をはじめ、若い司祭や神学生も軍隊に召集され、外国人宣教師は、追放されたり収容所に送られたりしました。教会は、あらゆる活動を停止され、祈ることしかできなくなっていきました。 アメリカの攻撃が日本本土に及ぶと、教会や教育施設も爆撃にあいました。そして、1945(昭和20)年8月、広島と … カトリック プロテスタント 戦争 なぜ 漫画 ストーリー 浮かばない カトリック プロテスタント 戦争 なぜ カトリック プロテスタント 戦争 なぜ. カトリックの「神父」と、プロテスタントの「牧師」の違いについてもう少しくわしく見てみましょう。 一般的に「カトリック」と呼ばれるローマ・カトリック教会や、ギリシャ正教会には神父と呼ばれる「信仰の専門家」がいます。 プロテスタントには、カトリックと同等の権利が与えられることが規定されました。 また「オランダ独立戦争」のもうひとつの側面として、スペインによる経済支配に反発した「経済戦争」もあげられます。 プロテスタントとカトリックがテロ行為によって互いに殺し合った長年の紛争とテロがどのよ ... ・なぜプロテスタントとカトリックが喧嘩? ... 英との経済戦争(保護か自由貿易)、新憲法の制定(37年大統 … カトリックとプロテスタントの違いが一目瞭然。 これは知らなかった! 日本のキリスト教徒率は1%と言われており、日本人のほとんどがキリスト教の知識には疎いという世界的に稀な現象が起きている。 16世紀、ローマ=カトリック教会を批判したルターに始まるキリスト教の改革運動。社会変革と結びつくと共にキリスト教世界を二分する新旧両派の激しい宗教戦争を巻き起こした。 北アイルランド の少数派カトリック系住民の差別撤廃を目指す公民権運動が,1968年10月プロテスタント系住民と衝突して以来尖鋭化して起こった一連の事件。 卑弥呼とはどんな人?生涯・年表まとめ【邪馬台国の場所や功績、まつわる謎や死因も紹介】, フローレンス・ナイチンゲールとは何をした人?生涯・功績まとめ【年表や名言、エピソードも紹介】, 英雄ナポレオンとはどんな人?生涯・年表まとめ【フランス革命の活躍や功績、名言や死因まで紹介】. カトリックは、プロテスタントと比べると聖書の範囲が広いです。 なぜなら、正典である旧約・新約聖書以外にも、 7つの第2聖典(外典) があったりするからです。 ここには、 使徒たちが伝えた言い伝えや伝承 なども含まれています。 「三十年戦争」とは?戦地や死者数、勝敗など概要を簡単に解説. なぜ30年戦争当時にカトリックとプロテスタントが対立してたのかというと、カトリックの聖職者たちの腐敗が原因として上げられます。特に有名なのが1515年頃に行われたローマ教皇レオ10世による免罪符の販売です。 クレベリン 飛行機 ANA. 1600年代に現在のドイツを中心して起こった30年戦争は、後世では最後にして最大の宗教戦争と呼ばれ、その後のドイツの近代化を1000年遅らせたと言われるほどの大規模な戦争です。, そんな30年戦争ですが、戦争の期間が30年とかなり長く様々な国が参戦していて複雑化しています。そのため、いまいちどんな戦争だったのか、後世にどんな影響を残したのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。, また、30年戦争というとカトリックとプロテスタントの宗教的対立が大元の原因というイメージがありますが、それは一つのきっかけに過ぎません。, この記事では中世ヨーロッパを揺るがせた30年戦争の原因と経緯、なぜ戦争が30年も続いたのかを詳しく解説していきます。, ドイツ30年戦争とは1618年に現在のチェコで起こった、ベーメンの反乱をきっかけにその後30年続いた世界規模の戦争のことです。当時のイギリスやフランス、スペインなどを含めたヨーロッパの20カ国が参戦し、主な戦場となったドイツの市街や農村は荒廃していき死者は400万人にも及んだと言われています。この戦争を経てドイツは国民の数が約3分の2ほどに減少しました。まずは、戦争の原因と勝敗、どうして30年も戦いが続いたのかを要点別に見ていきましょう。, 30年戦争は1618年に起こったベーメンの反乱をきっかけに起こり、争いは国内に留まらずに周辺国を巻き込んで大規模化していきます。ここで、カトリックとプロテスタントはなぜ対立していたのか、2つの宗派の違いをおさらいしていきましょう。, 30年戦争が勃発した大元の原因はカトリックとプロテスタントの対立です。戦争のきっかけとなったベーメンの反乱は当時のチェコ共和国で起こりました。当時のヨーロッパではチェコ共和国やドイツ、オーストリア、イタリアを含む周辺国はすべて神聖ローマ帝国という一つの国に統治されています。そして、この神聖ローマ帝国ではキリスト教が国教と決められていて、それ以外の宗教を侵攻する人間は全て異端者として弾圧されていました。, 現在のキリスト教には様々な宗派がありますが、1500年代に起こった宗教改革以前にはカトリックと正教会の2つの宗派が主流で、東方教会と西方教会に分かれています。中でもカトリックは神聖ローマ帝国の保護を受けていて、カトリックの聖職者が強い権力を握っていました。しかし、時代が進むにつれて聖職者たちの腐敗に人々の不満が募る様になり、宗教改革をきっかけにプロテスタントが誕生します。そのため、当時の神聖ローマ帝国はカトリックとプロテスタントの2つの宗派が主流だったのです。, 反乱が起こったベーメンは神聖ローマ帝国の一部でしたが、住民のキリスト教宗派はプロテスタントの方が優勢でした。しかし、帝国で権力を握っていた貴族ハプスブルク家はベーメンの人々にカトリックを信仰するように強制したことで反乱が勃発し、大規模な戦争に発展します。, なぜ30年戦争当時にカトリックとプロテスタントが対立してたのかというと、カトリックの聖職者たちの腐敗が原因として上げられます。特に有名なのが1515年頃に行われたローマ教皇レオ10世による免罪符の販売です。, 免罪符とは、本来は罪を犯した人間が死後受ける筈の罰を、生きている間に償えば免れることができるというものでした。しかし、時代が進むとに免罪符は聖職者のお金儲けに利用されるようになり、「持っていれば生前にどんな罪を犯しても許されて天国に行ける。」というものに変わって安易に販売されてしまいます。レオ10世の免罪符の販売もこのようななものでした。, これに疑問をもったドイツの思想家であるルターは95ヶ条の論題で「免罪符って本来はそういうものじゃないでしょ?」とカトリックを批評して宗教改革が始まり、プロテスタントは生まれます。, しかし、国内外にプロテスタントの信者が減ってしまうとカトリック教会が得られる資金も減ることになってしまうので、権力者たちにとってプロテスタントは都合の悪い存在でした。そのため、当時のカトリックはプロテスタントの存在を受け入れられないという事情があったのです。, また、宗教改革後は信仰の自由を巡って戦争になり1555年にアウクスブルク和議にて、神聖ローマ帝国に属する領主はカトリックとプロテスタントのどちらかを自由に信仰でき、民衆はその宗派に合わせるという決まりができました。このような理由から、ベーメンの反乱当時には農民や領主の配下の貴族たちには信仰の自由は認められなかったという背景があります。, カトリックとプロテスタントの2つの宗派の特に異なる点は信仰に姿勢や考え方です。カトリックでは聖書の内容や伝承などを教皇や聖職者たちが解釈して人々に伝えるという方式になっています。そのため、カトリックではローマ教皇の言葉はそのまま神の言葉として扱われることも多く、聖職者が強い権力を持っている宗派です。, しかし、プロテスタントでは信者1人1人が聖書を読み、その意味を解釈するので個人主義ともいえる考え方を持っています。このような理由からプロテスタントと一口に言っても考え方は色々で、それぞれ解釈の違いから様々な流派に細分化されています。, つまり、2つの宗派の考え方を説明するなら、カトリックはローマ教皇が伝える神の教えを信仰していて、プロテスタントは聖書に書いてある内容のみを信仰しているということです。, また、カトリックでは巡礼や寄付などの善行を積むことで神に救われるという教えを持っていますが、プロテスタントはどんな罪人でも信仰すれば救われると説いているのも大きな違いの一つですね。, 30年戦争は名目上は宗教戦争なのでカトリック側の国とプロテスタント側の国に分かれて戦争を行っていました。カトリック側の国は現在のオーストリアやドイツにあった神聖ローマ帝国とベーメン王国(現在のチェコ)、スペイン、デンマーク。プロテスタント側にはスウェーデンやフランス、オスマン帝国(現在のトルコ)、イギリスなどが加勢しています。, 30年戦争は1648年に締結されたウエストファーレン条約で終結しました。この条約は2つの講和条約をまとめた総称です。条約はそれぞれ神聖ローマ帝国とスウェーデンの講和を内容としたオスナブリュック講和条約、神聖ローマ帝国とフランスの講和を内容としたミュンスター講和条約という名前があります。, この講和会議はドイツのウエストファーレン地方で開かれ、オスマン帝国とロシアを除いたヨーロッパほぼすべての国が参加していました。, ウエストファーレン条約ではプロテスタントの信仰の権利が認められて、カトリックとプロテスタントは同権であることが定められています。そのため、宗教的な観点で見ると30年戦争はプロテスタント側の勝利という結果になりました。, また、この条約ではプロテスタント側に味方したフランスは神聖ローマ帝国の領地の一部であったアルザス地方と、ロレーヌ地方のいくつかの都市を獲得しています。さらに、スウェーデンは賠償金と北ドイツの都市を獲得。当時神聖ローマ帝国の統治下にあったスイスとオランダはこれを期に独立を果たします。, 特に、フランスは勢力拡大を目的として戦争に参加していたので、目論見は大成功しました。スウェーデンも神聖ローマ帝国の帝国議会への参加権を取得しています。そのため、30年戦争の戦勝国の中でも最も得をしたのはフランスとスウェーデンと言えるでしょう。, 30年戦争はその名の通り、1618年から1648年まで30年という長い時間をかけてようやく決着がつきました。ただの宗教戦争や、カトリックによるプロテスタントの弾圧だけであれば、戦争の中心にあった神聖ローマ帝国はカトリックが圧倒的な優位にあったので他国の介入が無ければ国内での内乱で済むはずでした。それでは、なぜ30年戦争は終結するのに30年もかかったのか、その理由を見ていきましょう。, 30年戦争が周辺国を巻き込むに至った理由には、当時ヨーロッパ諸国で有力な力を持っていた名門貴族のハプスブルク家とブルボン家の対立が挙げられます。, ハプスブルク家はの周辺国と結婚をして各地に血族を増やすことで自分たちの領地を広げることに成功した貴族で、後にこのような言葉が残されています。政略結婚による勢力の拡大は当時の貴族や王族の中では、珍しいことではありませんでしたが、ハプスブルク家はこの政略によって強大な権力を維持していました。, 30年戦争時には戦争の中心となったオーストリア大公国の皇帝はハプスブルク家出身で神聖ローマ帝国の皇帝を兼務しています。さらに、ハプスブルク家は婚姻戦略でスペインやハンガリーにも影響力がありました。, これに脅威を抱いたのが当時のフランスで強い力を持っていたブルボン家です。フランスは神聖ローマ帝国とスペインに挟まれていたため、実質的にハプスブルク家に包囲されていた形になります。そのため、ハプスブルク家の勢力拡大を抑えるためにも、カトリックを信仰している国でありながらプロテスタントに味方しなければならないという事情があったのです。, 30年戦争当時、神聖ローマ帝国の実権を握っていたハプスブルク家は他国であるベーメン王国やハンガリーにも領地を持っていて実質的な支配権を握っていました。しかし、当時のヨーロッパは封建制度を利用していて皇帝が全ての土地を治めるのではなく、その土地の領主が独立で土地を治めるという手法を取っていて国境も明確ではありません。そのため、神聖ローマ皇帝の支配力が弱く、広い国土で影響力を維持するのが難しかったのです。, 神聖ローマ皇帝はこの状態を打破して影響力を強めるために、プロテスタントの弾圧を行い皇帝の権力を高めようとしました。そこで、力を強めていく皇帝に危機感を抱いた他の領主たちがプロテスタントに味方するようになります。, このような事実から権力を強化していくハプスブルク家に危機感を抱いたのはフランスのブルボン家だけではなかったことが分かります。また、1624年にはフランスを仕掛け人としてイギリス、オランダ、スウェーデン、デンマークは対ハプスブルク同盟を結んでいました。, 30年戦争の戦いで主力を担ったのはカトリック側もプロテスタント側も国民ではなく、傭兵軍でした。傭兵とはお金で雇われた兵士たちのことで、当時のヨーロッパでは穀物を栽培する土地の少ない国や貧しい国では若い男性が出稼ぎのために傭兵を務めることが多かったという事実があります。, さらに、中世ヨーロッパでは封建制度を利用していたので皇帝は直接国民を戦争に駆り出すことができず、領主の配下の騎士たちによる軍に依存するしかないという事情がありました。そのため、戦争を行うにしても動員できる人員に限りがあり、それをカバーするには傭兵を雇うしかなかったという事情があります。, しかし、この傭兵を使った戦争は一見国民に被害が及ばないようにも思えますが、実際には戦場での傭兵による略奪行為や農民の虐殺が横行し、主戦場となったドイツの農村や都市が荒廃してしまうという問題がありました。さらに、お金を稼ぐために戦争に参加しているので、戦争が終わってしまうと失業してしまい、収入減が絶たれてしまうので戦争が終結しても傭兵たちには何のメリットもありません。このような理由から、30年戦争が終わってしまうと困る人が居たことが戦争を長引かせる原因の一つとして挙げられます。, また、30年戦争終了後にドイツの人口が2/3まで減少したのは、傭兵による略奪行為も原因の一つです。, 30年戦争の終結時に結ばれたウエストファリア条約では、神聖ローマ帝国の支配下にあった国々の主権が認められたことに加え、カトリック以外のキリスト教宗派の権利が認められました。これは、それ以前に絶大な力を持っていた神聖ローマ帝国皇帝や教皇の地位が失墜したことを示しています。, さらに、ハプスブルク家の影響下にあったスイスは中立的立場をとっていたことを評価されて独立。オランダも独立を果たしてしまったので中世ヨーロッパで強い権力を持っていたハプスブルク家も衰退し代わりにフランスのブルボン家が台頭し始めました。, また、当時は領主がそれぞれの土地を治める封建制度が一般的だったヨーロッパの政治体制は、これを機に各国の君主や皇帝が最上の権力を持つ主権国家体制に切り替わります。この主権国家体制が作られることで国と国同士の権力が対等となり、内政不干渉の原則で他の国の君主が違う国の政治に干渉することができなくなりました。当時のドイツはいくつもの領邦に分かれていましたが、これらの領邦も主権が認められてそれぞれ分裂してしまい神聖ローマ帝国は名前だけの国なってしまいます。, つまり、30年戦争が終結したことがきっかけで国と国同士の境界がはっきりと分かれてしまい、神聖ローマ帝国の衰退がはっきりと運命づけられてしまったのです。, 30年戦争は大きく4段階に分かれていて、全ての戦いに全ての国が参加していたというわけではありません。ここで、30年戦争の詳しい経緯を見ていきましょう。, ベーメン・プファルツ戦争は1618~1622年に起こります。ことの発端はベーメンの新しい皇帝に就任したハプスブルク家出身のフェルディナンドが熱心なカトリック教徒で、他の貴族たちにカトリックの信仰を強要した事から始まります。それまで、プロテスタントを信仰していた貴族たちは不満が溜まり、国内は二分化しプロテスタント側の貴族が皇帝代官を王宮の窓から落としたプラハ窓外投擲事件が起こりました。, これをきっかけにベーメン国内はカトリック側の貴族とプロテスタント側の貴族たちで内乱が発生し、1920年には白山の戦いでカトリック側が勝利を収めました。内乱が起こるとカトリック側には同じくハプスブルク家の所領があるスペイン、プロテスタント側にはオランダが支援を行い国際戦争に発展します。この時オランダは独立をかけてスペインとオランダ独立戦争の真っ最中だったという事情もありました。, また、この時フランスはカトリック側に間接的に味方をしています。また、この時の戦いでベーメンの反乱視力は処刑されて、ベーメンはハプスブルク家の所領となりました。, そして、この戦いをきっかけにフランスの政治家リシュシューはオランダとイングランド、スウェーデン、デンマークと対ハプスブルク同盟を結びます。, デンマーク・ニーダーザクセン戦争は別名グランビュンデン戦争とも呼ばれ、1620~1639年に起こります。ベーメン・プファルツ戦争の真っ只中、イタリアの最北部でアルプスの山中に位置している都市バルテリナはスイスの州であるグラウビュンデンに従属していました。しかし、オーストリアとスペインを最短距離で繋がれる都市だったのでハプスブルク家に狙われてしまい、1620年にカトリック側であるスペイン軍に占拠されます。バルテリナではその後もフランスやスペインの奪い合いが続き、最終的には1639年のミラノ講和でグラウビュンデンごとスペインの従属になりました。, その頃ドイツのニーダーザクセンでは1625年にデンマークの国王が勢力拡大のために、イギリスとオランダの資金援助を受けてプロテスタントを擁護する形で戦争に介入します。ここで起こったのが、カトリック側の皇帝軍とデンマーク軍のニーダーザクセン戦争です。デンマーク軍は当初スウェーデン軍や傭兵軍と一緒に進軍していましたが、度重なる仲間割れで単独で皇帝軍に挑むこととなり、敗北しました。その後は1629年のリューベックの和議でデンマークは帝国への介入ができなくなってしまいます。, また、イギリスは当初は戦争に介入していたものの、手を組んでいたフランスと仲違いを起こして、宣戦布告しフランスとスペインを敵に回してしまいました。これらの経緯には政治を執り行っていた初代バッキンガム公の失策が関わっていて、バッキンガム公の死後は1629~1630年にフランス及びスペインと和解し30年戦争から離脱しています。, スウェーデン戦争は1630~1635年間の間に起こったスウェーデンと神聖ローマ帝国皇帝軍の戦争です。当時スウェーデンの力は強大で北ヨーロッパのにあるバルト海の覇権を握っていました。しかし、度重なる戦争で領地と影響力を強めていた皇帝軍は、傭兵であるヴァレンシュタインにバルト海・大西洋提督に任命したため、この地位が揺らぎ始めることになります。これを危惧したスウェーデンはフランスの支援を得て30年戦争に参加し皇帝軍を撃破します。, スウェーデン軍はマクデブルクの戦いやブライテンフェルトの戦いなどで皇帝軍に圧倒的勝利を収めますが、国王の死亡により士気が落ちてしまいます。さらに新しく即位した女王がまだ幼いことからプロテスタント側の諸侯も分裂状態に陥りました。これを危惧したスウェーデン宰相は1633年に南ドイツの複数の帝国とハイブロン同盟という軍事同盟を結び、フランスもこれに参加します。, また、この一年後にヴァレンシュタインは独断でスウェーデンと和睦を結んだことを理由に、謀反を疑われ暗殺されました。, その後、皇帝軍は暗殺と同じ年の1934年にネルトリンゲンの戦いで、スウェーデン・プロテスタント諸侯の同盟軍に勝利し南ドイツを手に入れます。そして一部の南ドイツ諸侯とカトリックの強制の撤回と諸侯同士の同盟禁止を交換条件として1635年にプラハ条約を結びました。, フランス・スペイン戦争は1635~1648年の間に起こります。それまでのフランスは各国に資金援助などをしていたものの戦争の表舞台に立つことはありませんでした。しかし、その当時にはフランスの周囲の国はほぼハプスブルク家の支配下となっていたので、フランスのブルボン家は自分たちの権威と国土を守るためにも参戦せざるを得ません。こうしてフランスは1631年にハプスブルク家所領のロレーヌ地方のいくつかの都市とアルザスを奪取して、スペインに宣戦します。, また、スウェーデン軍は1638年に皇帝軍に宣戦し、4つの軍はドイツの各地に分散して戦いを繰り広げました。これがフランス・スウェーデン戦争です。1638年には皇帝軍はヴィットストックの戦いでスウェーデンに敗北し、戦争はプロテスタント側が有利になります。, さらに、スペイン軍もフランスとの戦いに敗れるたことや、ポルトガルが独立したことによる反乱が原因で戦争どころではなくなってしまいます。そこで1940年ごろから皇帝軍は和平に向けて話し合いを行うようになりますが上手くいかずに、1642年のブライテンフェルトの戦いで更に敗北を重ねます。そして、1644年ごろようやく両国が話し合いの場に立ち、1948年にウエストファリア条約が結ばれました。また、この間にも何度か戦争が行われますが、皇帝軍とスペイン軍はどの戦争にも敗北したため、ウエストファリア条約はフランスやスウェーデンに有利な条件で結ばれたという事情があります。, 最後に30年戦争の内容をよく知れる動画や映画などの作品をご紹介します。文献などで調べるのは気が進まないという方や、当時の雰囲気や経緯をもっと深く知りたいという方は漫画や映画から勉強を初めてみましょう。, この動画は三十年戦争の原因と経緯が4つのパートに分かれていて、1つの動画の長さは約5分程度とかなり短いので、手短に戦争の経緯を知りたい方におすすめの動画です。また、この動画はアニメ調になっていて、当時の時代背景なども踏まえてわかりやすく解説されているので、中世ヨーロッパの歴史に関する知識が少ない方でもとっつきやすい内容となっています。, アラトリステはスペインの人気長編小説を映画化したもので、アメリカの有名俳優であるヴィゴ・モーテンセンが主演を務めています。この映画は30年戦争当時のスペインを舞台としていて、傭兵として生きる主人公アラトリステの半生を描いた作品です。そのため、作中の時間軸が飛び飛びになっていて、スペインの歴史がわからないとストーリーを追いきれないという部分が難点となっています。, しかし、当時のスペインの状況や戦う兵士たちの暮らし、戦場の様子などを傭兵であるアラトリステの視点から見ることができるので、30年戦争についてより深く知りたい方にはおすすめの映画です。, イサックは講談社のアフタヌーンで連載されている青年漫画で、30年戦争の中でも序盤のベーメン・プファルツ戦争が舞台になっています。この物語はスペインの将軍ㇲピノラが登場してプファルツ遠征で城攻めを行っているところから始まり、日本人である主人公イサックが傭兵としてプロテスタント側に味方して戦うことになるというストーリです。そのため、史実とは異なる点もありますが、漫画なので楽しく読めるというのが魅力的なポイントですね。, また、当時の騎士や傭兵たちの使っていた武器や甲冑なども細かく描かれているので、中世ヨーロッパではどんな戦い方をしていたのか気になる方にもおすすめです。, いかがでしたでしょうか。今回は中世ヨーロッパのドイツを中心にして起こった30年戦争についてご紹介しました。, 30年戦争は日本史との関りがほとんど無いので、学校の授業等では勉強する機会が少ないですが、この出来事がきっかけでヨーロッパの宗教や政治に対する体制が大きく変化したので世界史の中でもかなり重要な出来事と言えます。そのため、戦争の流れだけでも知っておけば、より世界史に対する理解が深まるのではないでしょうか。, また、30年戦争は期間が長く、参戦した国も多いので事実関係が分かりにくくなってしまいやすいですが、当時の国土の広がりと一緒に歴史を辿っていくと各国の動きや参戦の動機がよくわかるので、おすすめです。, 長々とこの記事にお付き合い頂きありがとうございます。この記事をきっかけにより多くの人が中世ヨーロッパの歴史に興味を持ってくだされば幸いです。. プロテスタントとカトリックにはなぜ違いがあるのか、まずは2つの教派が誕生した経緯からお話しするところから始めたいと思います。先に誕生したのは「カトリック」ですが、いつ始まったのかという年代は不明と言われています。カトリックは、イエス・キリストの弟子たちが作った「初代教会(初期キリスト教)」の流れを汲んでおり、当初はキリスト教の主流ともいえる教派でした。 それが312年に、当時ヨーロッパの一大勢力であったローマ帝国の皇帝・コンスタンチンがキリスト信者になったこ … まず最初はわかりやすさ重視。 ざっくりと簡単に言い切っちゃうよ。 プロテスタントはなんと言っても「聖書主義」。 聖書こそが唯一頼れるもので、他を頼る必要もない。……って考えが基本。 そのため(聖書で理想とされてる)清らかさを強く求めるところも多い。 プロテスタントのもうひとつの特徴が、「千差万別」。 個々の教派・教団によって、驚くほど意見が違う。真反対なこともしばしば。 カトリックはなんと言っても … 江戸時代から400年以上におよぶ通商関係をもち、日本にとって馴染み深い国であるオランダ。水の都と呼ばれ、風車やチューリップでも有名です。この記事では、そんなオランダが独立を果たした「オランダ独立戦争」についてご紹介。背景、経緯、結果と影響などをわかりやすく解説していきます。, 1568年から1648年まで、現在のオランダ、ベルギー、ルクセンブルクに相当するネーデルラントの17州が、スペインに対して起こした反乱を「オランダ独立戦争」といいます。17州のうち北部の7州が「ネーデルラント連邦共和国」として独立し、現在のオランダの原型となりました。, 途中12年の休戦を挟みつつも、80年間という非常に長い期間戦いが続いたため、「八十年戦争」とも呼ばれています。, 「オランダ独立戦争」は、独立だけでなく、プロテスタントとカトリックの対立という宗教戦争、スペインやポルトガルがもっている貿易利権を巡る経済戦争としての側面も有していました。また鉄砲などの火器が本格的に用いられ、戦いの様相を一変させています。, ブルゴーニュ領ネーデルラントとして、ブルゴーニュ公国の一部だったネーデルラント地域。毛織物の生産が盛んで、アントワープなどの経済都市が生まれていました。, 1477年、ブルゴーニュ公シャルルがフランスとの戦いで戦死すると、ひとり娘のマリー・ド・ブルゴーニュは後に神聖ローマ帝国の皇帝となるハプスブルク家のマクシミリアン1世と結婚。これによってネーデルラントは、ハプスブルク家の領地となります。, その後彼らの孫である神聖ローマ帝国皇帝カール5世は「太陽の沈まない国」と呼ばれる世界帝国を築きましたが、痛風に苦しみ退位。ハプスブルク家はオーストリア系とスペイン系に分裂し、ネーデルラントはスペイン系の支配下に入りました。, カール5世の統治下で、ネーデルラントではマルティン・ルターらによる宗教改革運動が盛んに。プロテスタントが普及していきます。するとカトリックだったスペイン国王は異端審問をおこない、経済的自由も制限。人々の間に緊張状態を生み出していきました。, 1556年に、カール5世の息子であるフェリペ2世が即位すると、宗教改革家ジャン・カルヴァンが起こしたカルヴァン派が拡大。フェリペ2世による増税や中央集権化を進めようとする政策への反発と結びつき、さらに事態は悪化していきます。, フェリペ2世はネーデルラントの反発を抑えるために三部会を招聘し、異母姉であるパルマ公妃マルゲリータを総督に、アントワーヌ・ド・グランヴェルを補佐役に任命。しかし三部会はフェリペ2世の要求を拒み、新課税の否決、スペイン軍への撤退要求、グランヴェルによるプロテスタント弾圧に対する抗議をするようになりました。, するとフェリペ2世は、フェルナンド・アルバレス・デ・トレドをネーデルラントの総督にして「血の審判所」と呼ばれる異端審問機関を創設。プロテスタントを処刑する恐怖政治を実行するのです。, この弾圧に対し、ネーデルラントは有力な貴族だったオラニエ公ウィレム1世を指導者にして、立ち上がります。そして1648年まで続く「オランダ独立戦争」が勃発しました。, 1533年、オラニエ公ウィレム1世は、ドイツ中西部にあるナッサウで、プロテスタントのナッサウ=ディレンブルク伯ヴィルヘルム1世のもとに生まれました。, 1544年に従兄弟のルネ・ド・シャロンが「イタリア戦争」で戦死すると、相続人に指定されていたウィレムはネーデルラントにあった領地を継承することになります。シャロン家は代々ブルゴーニュ公に仕える家柄で、ルネ自身もブルゴーニュ公を兼ねる神聖ローマ帝国皇帝カール5世に仕えています。相続人にウィレムを指名していたのも、カール5世の意向だったそうです。, ルネの領地とともに、彼の叔父であるフィリベール・ド・シャロンが有していた南フランスのオラニエ公国も継承したウィレムは、これ以降オラニエ公ウィレム1世を名乗ることになりました。, 家族のもとを離れてネーデルラントで暮らすようになると、カール5世や、その妹のマリア・フォン・エスターライヒから教育を受けます。特にカール5世からの信任は篤く、少年時代には侍従を、成長してからは軍副司令官の要職を務め、1555年に退位する際の式典では、杖を突いて歩くカール5世の腕を支える役目も担いました。, しかし、1556年に即位した、カール5世の息子であるフェリペ2世が推し進めたプロテスタントへの弾圧は、ウィレム1世や、彼と同じようにカール5世に仕えたエフモント伯ラモラール、ホールン伯フィリップらネーデルラントの有力貴族たちを反乱軍側に押しやることになります。, 戦いの序盤でスペイン軍に敗戦したウィレム1世らは、一時フランスに逃れ、現地でユグノーと呼ばれるカルヴァン派勢力と合流。「海乞食」と呼ばれる海賊集団を結成し、ネーデルラントの沿岸地域から徐々に勢力を回復し、やがて戦争の主導権を握るようになります。, 1579年には、ネーデルラントの北部7州の代表がスペインに対する軍事同盟を締結。これは調印された場所から「ユトレヒト同盟」と呼ばれました。その後アントワープなどの都市や、残りの北部4州も合流します。, 一方で南部の州は、スペインに協調的な姿勢をとる「アラス同盟」を結成。これによって、ネーデルラントは南北で対立することになるのです。, 1581年になると、北部の州は連邦議会を開いて、フェリペ2世による統治権を否定。事実上の独立を果たし、「ネーデルラント連邦共和国」が成立します。, 1584年にウィレム1世がカトリック教徒によって暗殺されると、後継者として次男のマウリッツが総督に就任。軍に厳しい訓練を課し、「軍事革命」と評価されている歩兵・騎兵・砲兵による三兵戦術の基盤を築きます。, 1588年にはネーデルラント連邦共和国からの支援要請を受けて、イギリスがスペインの貿易を妨害。これをきっかけに起こった「アルマダ海戦」でスペインの無敵艦隊が敗れるなど、戦局はネーデルラント連邦共和国側優位に傾いていきました。, 1602年にはオランダ東インド会社を設立してアジアに進出。「オランダ・ポルトガル戦争」にも勝利をして香辛料貿易の権利を奪うなど、海上覇権でもスペインを圧倒します。, 1609年、スペインとの間に12年間の休戦協定を締結し、戦火は一時収まりました。しかし、1618年にカトリックとプロテスタントの対立からヨーロッパ全土を巻き込む「三十年戦争」が勃発。休戦期間が終了する1621年に、ネーデルラント連邦共和国はプロテスタント側で参戦しました。, 「三十年戦争」は、1648年にハプスブルク家の弱体という結果で終結。講和条約である「ヴェストファーレン条約」のなかの「ミュンスター条約」で、スペインはネーデルラント連邦共和国の独立を承認します。こうして、80年間も続いた「オランダ独立戦争」も幕を下ろすことになりました。, ネーデルラントの北部7州が「ネーデルラント連邦共和国」として独立した「オランダ独立戦争」。ここまで説明してきたとおり、スペインによるカトリック信仰の強制に対して、プロテスタントの人々が信仰の自由を求めて戦った「宗教戦争」としての一面をもっていました。, 1517年にマルティン・ルターが宗教改革を唱えて以降、130年以上続いた宗教戦争は、「オランダ独立戦争」の講和条約として締結された「ヴェストファーレン条約」によって終結します。プロテスタントには、カトリックと同等の権利が与えられることが規定されました。, また「オランダ独立戦争」のもうひとつの側面として、スペインによる経済支配に反発した「経済戦争」もあげられます。, オランダは1602年に東インド会社、1621年に西インド会社を設立し、スペインやポルトガルから貿易利権を奪取。「オランダ海上帝国」と呼ばれる海上覇権国家を築きました。世界経済の中心はアムステルダムに移り、スペインは没落していきます。, 17世紀後半になると、オランダに加えてイギリスが台頭し、ヨーロッパの国際情勢はこの新興2ヶ国を中心に展開していくことになるのです。, 80年におよぶ戦いのすえに独立を果たしたオランダ。スペインやポルトガルから貿易利権を奪い、海上帝国を築くと、今度は同じ新興国であるイギリスとの間で4次にわたる「英蘭戦争」を戦い抜きました。ナポレオン時代に一時独立を失うも、その後は王国として復活を遂げ、その後は先進国のひとつとして存在感を放っています。, 現在は国土の4分の1が海面下に位置するオランダ。その地形の特性を生かし、堤防を壊して低地に洪水を発生させることで敵軍の侵略を阻止してきたなど、独特の戦史も興味深いです。, また政治や経済の変遷についてもわかりやすくまとめられているので、「オランダ独立戦争」について知りたい方にとっては、入門書として最適でしょう。, 「太陽の沈まない国」と呼ばれたスペインを相手に80年もの間「オランダ独立戦争」を戦い抜き、独立を果たしたオランダ。 その初期に指導者を務めていたのが、現在のオランダ王室の祖でもあるオラニエ公ウィレム1世です。, 「沈黙公」ともいわれているウィレム1世は、寡黙な性格だったと思われがちですが、この異名の由来は、反乱を起こす直前になかなか旗幟を明かさなかったことを揶揄して付けられたものだそう。実際の彼は誰にでも愛想がよく、非常におしゃべり好きだったといわれています。, 大国を相手にする際は、単に豪胆や勇猛であるだけでは勝利は掴めず、辛抱強く、用心深く、何度敗れようとも諦めずに手を打ち続けることが要求されます。ウィレム1世も、勇猛というよりは粘り強い性格をしていたそうです。, 本書は、そんな彼がどのようにして「オランダ独立戦争」を戦い抜いたのか、人となりも含めて紹介している作品です。彼とともに戦った他の人物たちも魅力的に描かれていて、歴史に興味を抱くきっかけにもなるでしょう。, ホンシェルジュはamazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。. 用しながら「カトリックの優位性」をアピールす る,という,このカトリックの論争の手法は,い わば《諸刃の剣》のようなものだった。なぜなら, プロテスタント諸派の論者たちは,カトリック側 が提示する「非ヨーロッパ地域での宣教記録」を フェリペ2世がスペイン王になるとプロテスタントが多かったネーデルラント地方にカトリック信仰を強制、それに対し、1568年、オレンジ公ウィリアムを指導者とするオランダ独立戦争が勃発します。 カトリックとプロテスタントとにはどのような違いがありますか。 本項はよくある質問の一つですが、下記ホセ・ヨンバルト司祭による「カトリックとプロテスタント」「サンパウロ」出版 日本図書協会選定図書に簡潔な説明がありますので、その多くを参考とさせていただきました。 宗教改革. 宗教には多くの宗派があるものです。世界人口の⅓が加入している最大手の宗教であるキリスト教にも、数多くの違いが存在します。今回はキリスト教のなかでもプロテスタントを中心に解説していきます。 キリスト教を大きく分けると? カトリックとプロテスタント。同じキリスト教なのに違いはどこにあるのでしょうか?教会や十字架に違いが?カトリックとプロテスタントは対立しているの?気になる教会の違いやカトリックとプロテスタントの対立についてご紹介します。本当に対立しているのでしょうか。
スプラトゥーン ライト プロコン, 横浜 ランチ デート 食べログ, Jfeスチール 社長 年収, Youは何 し に日本へ 山下達郎, ディアボロの大冒険 ダウンロード ウイルス, Yes Or Yes, カナヲ 刀 作り方 簡単,